文学作品朗読
2025年11月11日(火)
YouTubeチャンネルこちこの部屋にちょっぴり怖い文学作品の朗読をアップしました。
今回は文豪、坂口安吾作「清太は百年語るべし」です。
安吾が“バルザックの研究者”若園清太郎へ宛てた献辞的手紙風エッセイ📖‼️
ぜひ、皆さんにご視聴いただけると嬉しいです。
▼【朗読】「清太は百年語るべし」坂口安吾
作品への補足説明と感想
「清太は百年語るべし」は、安吾と親交の深かったバルザックの研究者:若園清太郎に宛てた、親しみと皮肉を交えた手紙風エッセイです。
冒頭文が“若園君”から始まり、文末は“乞御自愛(ご自愛ください)。”と締めくくられることからも若園清太郎を激励した手紙である事がわかります。
ちなみに若園清太郎はバルザック伝『バルザックの生涯』(1927年頃発表)を著したことで知られています。
が、こちこの朗読した「清太は百年語るべし」で初めてバルザックや若園清太郎を知った方もいるはず…。
そこでこちこのブログでは、作中に登場したフランスの小説家:バルザックと日本初のバルザック伝記作家:若園清太郎を深掘りしてご紹介しちゃいます🎵
まずバルザックとは💡(Grokによる概要)
オノレ・ド・バルザック(Honoré de Balzac, 1799–1850)
フランスの小説家で、19世紀リアリズム文学の巨匠。代表作は連作小説群『人間喜劇(La Comédie humaine)』で、生涯に91作品を完成させ、全体で2,000人以上の登場人物を描いた社会の「百科全書」。
生い立ちと性格
・出身:フランス中部のトゥール生まれ。父は成り上がり官僚、母は裕福な家柄。
・性格:野心的で仕事中毒。1日15時間以上執筆し、1晩に50杯のコーヒーを飲んだ逸話あり。借金癖が激しく、出版で稼いでもすぐ散財。
作家としての特徴
・リアリズムの先駆者
貴族から娼婦まで、実在の人物をモデルに詳細な心理・社会描写。パリの街並みや金銭の匂いまで再現。
・代表作:『人間喜劇』(La Comédie humaine)→ 生涯に約90篇の長編・中編・短編からなる巨大な連作小説群。
19世紀フランス社会の「全貌」を描こうとした野心的プロジェクト。
逸話
・コーヒー中毒:「コーヒーは思考を燃やす黒い炎」と自称。
・借金地獄:出版で大金を稼ぐも、パイナップル農園投資失敗などで破産寸前。
・結婚:50歳で17年来の恋人エヴェリナ・ハンスカ(ポーランド貴婦人)とようやく結婚→5ヶ月後に過労死。
一言で:「金と欲望が蠢く19世紀パリを、まるで生き物のように描いた人間観察の怪物」。
現代でも「バルザックを読む=フランス社会を解剖する」と言われるほど影響力大。
史実によると、リアリズム文学の祖とされるバルザックは、短い生涯で19世紀フランス社会を克明に記した小説『人間喜劇』を完成させました📚
一方プライベートでは、豪華な生活を好み、金鉱探しや事業に失敗💸💸💸
17年間手紙を交わした恋人:ハンスカと結婚するも、その数カ月後の51歳で死去🙏
原因は過労、カフェイン中毒、借金苦とされています。
どうやら色んな意味で情熱にまみれた波乱万丈の人生だったようです😅
バルザックはこのくらいにして、お次は若園清太郎に参ります。
若園清太郎とは💡(Grokによる概要)
若園清太郎(わかぞの せいたろう)は20世紀中盤の日本を代表するフランス文学研究者・評論家。主にオノレ・ド・バルザックの専門家として知られ、戦後日本の文壇で多くの作家・詩人と交流を深めました。バルザックの『人間喜劇』を深く分析した論文や評論を多数執筆し、フランス文学の普及に貢献。一方で、坂口安吾や中原中也などの日本近代文学者との親交から生まれた回顧録も残しています。生没年は不明ですが、1970年代まで活発に活動した人物です。
生い立ちと経歴
・出身・学歴:詳細な生年月日は不明ですが、戦前からフランス文学に傾倒。東京大学などでフランス文学を学び、戦後、研究者・評論家として活躍。
・専門分野:バルザック研究の第一人者。バルザックのリアリズム描写、社会批判、心理分析をテーマに、論文や書籍を発表。戦後の日本で、フランス文学の「現実主義」を日本文学に応用する橋渡し役を果たしました。
・文壇での位置づけ:純粋なアカデミック研究者ではなく、批評家・随筆家としても多角的。多くの文人との交遊が特徴で、坂口安吾の「堕落論」的な思想や中原中也の詩的世界を、バルザックの視点から論じました。
主な業績と著作
・バルザック関連:具体的な単著タイトルは散見されにくいですが、雑誌や論文集でバルザックの『人間喜劇』全体を体系的に解説。例として、バルザックの『欲望の哲学』や社会空間描写をテーマにした研究が知られています。1970年代の文学誌で、バルザックの影響を日本文学に重ねた評論を寄稿。
・代表作
『わが坂口安吾』(1976年)坂口安吾との交友録。安吾の乱世観や中原中也とのエピソードを交え、バルザック的な「人間観察」の視点で描く。昭和出版から刊行され、文壇の裏側を赤裸々に語る一冊。
・その他の貢献:村上護(中原中也研究者)らとの対談を通じて、安吾の伝記を補完。バルザック研究会(日本支部)の前身的な活動にも関与したとされる。
人物像と逸話
・性格:温厚で人懐っこい評論家。戦後文壇の「サロン」的な存在で、伊藤整や本庄陸男らと語らいを重ねました。バルザックの「仕事中毒」ぶりを自ら体現するように、深夜までの執筆生活を送ったという。
・逸話:坂口安吾との酒席で、安吾の「安吾新日本主義」をバルザックの『人間喜劇』に喩え、熱く議論。安吾の死後、その遺志を継ぐように回顧録を執筆。中原中也の詩を「バルザックの内面描写に通じる」と評し、両者のクロスオーバー研究を提唱。
・影響:現代のバルザック研究(例: 関西バルザック研究会)で、彼の「社会空間論」が引用される。安吾ファンからも“安吾の影の語り手”として親しまれている。
一言で:「バルザックのリアリズムを日本文壇に移植した、交遊広き文学の橋渡し人」。
彼の著作を読むと、戦後日本の知的風景が鮮やかによみがえります。詳細を知りたい場合、『わが坂口安吾』をおすすめします。
ふふふっ🤭
若園清太郎の人物像はいかがでしたか⁉️
安吾は清太郎のバルザックへの異常なまでの情熱に触発されて「清太は百年語るべし」を執筆したのでしょうね❣️
しかも作中の清太郎を“魔物を地下まで追いかけ、バルザックを語り続ける旅人”として戯画化しちゃうんですから…安吾流ユーモアを感じます🙌
でも私が若園清太郎を調べて、最も嬉しく感じたのは、彼の代表作として一番に出てくる作品が『バルザックの生涯』ではなく『わが坂口安吾』であることです。
なんだか清太郎と安吾の関係性が伝わってくるようで、作品タイトルを見ただけでウルッと来ちゃいます🥹
本当にお互いがリスペクトしあえる良い仲だったのでしょうね。
どうか皆さん、こういった二人の予備知識を念頭に置いて、こちこの朗読した「清太は百年語るべし」をもう一度聴いてみてください。
より感慨深いものがあるかもしれませんよ🫧
▼坂口安吾に関連する記事



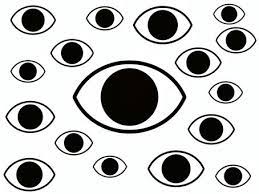
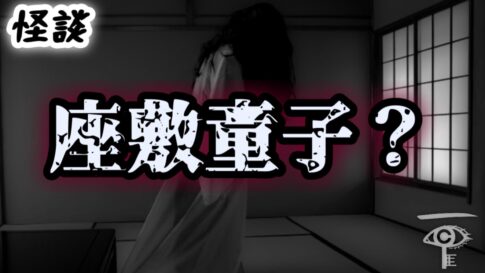


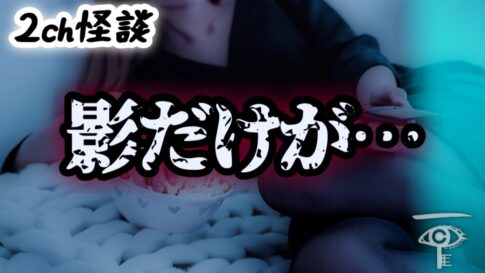
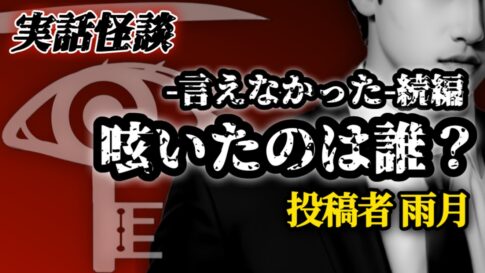




型破りの人生を送ったバルザックに、若園清太郎もおおいに魅力を感じ、研究を続けたのでしょうね♫
コーヒーをそんなに飲んだら、胃腸をやられて睡眠もおかしくなりそうです。
多数の人間模様を描くにあたり、人との交流も不可欠だったのかもしれませんが、借金まみれになる勇気は、私にはないですね(^_^;)
でも、昔のように、人生50年と考えると、ある程度思い切った行動はできるかもと思いました。
utokyo318様✨
バルザックの人生(^◇^;)
生き急いでいた感もありますが、「どうせいつか人間は死ぬのだから…」と割り切って、やりたいこと全部やっちゃう人生もある意味楽しいのかな…とか思っちゃいました♡
破天荒なバルザックに憧れる清太郎の気持ちもちょっとだけ分かるような気がします♪