文学作品朗読
2025年9月29日(月)
YouTubeチャンネルこちこの部屋にちょっぴり怖い文学作品の朗読をアップしました。
今回は文豪、坂口安吾作「山麓」です。
安吾初期の短編小説📖‼️
主人公が疲労困憊の折に、遠い山麓の信夫の家を訪れ、そこで出会った一人の女性(信夫の妻)との出会いを描く…。
ぜひ、皆さんにご視聴いただけると嬉しいです。
▼【朗読】「山麓」坂口安吾
朗読エピソードと作品への感想
初めに、坂口安吾の短編小説「山麓」をAIによる概要でご紹介します💁♀️
▼坂口安吾「山麓」とは💡
坂口安吾の短編小説「山麓」は、青空文庫で公開されている作品であり、短く、約5分程度で読めます。この作品は、坂口安吾の作品集『逃げたい心』や『坂口安吾全集』などに収録されており、短時間で読める作品なので、坂口安吾の世界に触れる入り口として手軽に読むことができます。
では、私の朗読エピソードと感想に参ります✨
こちらの作品を青空文庫で初めて読んだ日、私は“この作品、本当に小説なの?”と思いました。
なぜなら登場人物である主人公の名前が明かされていないため、私は冒頭の一節『あの頃私は疲れてゐた。遠い山麓の信夫の家で疲れた古い手を眺めてゐた、あの頃。』という前置きから“この作品は安吾の随筆✏️”と、バイアスがかかってしまったのです。
そのため“主人公=安吾ではない”と理解すべく、私は何度も「山麓」を読み返すハメに…👀💦
そしてやっと“主人公=安吾ではない”と確信した私。
これには正直言って“やられた‼️安吾の術中にハマってしまった🤦♀️”と思ってしまいました〜。
特に小説の冒頭文は、非常に重要な章となるため、物語の全体像を示したり、聞き手の注意を引いたりする内容が置かれます。
私は「山麓」の冒頭文で“安吾が療養もしくは静養するために訪れた土地での回想なのだろう”と勝手に思い込んだのです。
いや〜、さすが安吾👍‼️
魅せてくれるじゃないか〜🥰
私は文豪、坂口安吾の世界観に出だしからハメられてしまったことに(ただの固定観念ですが💦)、なぜか嬉しくなっちゃいました💘
そんな経緯もあり、せっかくなので朗読も私がインスピレーションで感じた主人公=安吾になりきって表現しちゃいますよ〜。
ちなみに、作中に登場するアイヌ族の男“信夫”の人名はノブオではなくシノブと読ませていただきました。
理由は、人名に振り仮名表記がない場合、安吾は自分の作品でよく同じ人名を使い回すという記事を読んだことがあるからです。
よって「山麓」の“信夫”には振り仮名がなく、一方別の作品では“信夫”と書いてシノブという人が登場していたので「山麓」での“信夫”もシノブと読む事にしました🎶
それからサムネイル画像は、今回もいつも通りXの生成AI Grokに細かく注文を付けて作成しちゃいますよ〜🎨
Grokへのリクエストは『白樺の林、寒そうだけど雪は降っていない風景を描いて』です📱
▼そして生成された画像がこちら

おぉーーー🤩
雰囲気ある〜🍂
Grokを使ってサムネイルを作ってきた中で、過去一良い仕上がりかも👏👏👏
続いて朗読に関してですが、私は精神的に疲れた男を演出するために「山麓」はため息混じりの声で表現しました〜😮💨🫧
と、こんなふうにして朗読と編集を終えた私はこちこの部屋に「山麓」をアップ⤴️
もうねっ🎶
「山麓」をアップしてからの私は自分の朗読を5回も聴いちゃいました〜👂‼️
というのも「山麓」は結構好きなテーマで、朗読したことで、より安吾から深いメッセージを受け取ったような気がしたからでーす🎁✨
私が思うに…🤔
坂口安吾は生きることにとても執着した人なんじゃないかなと。
最近ニュース記事でも読んだのですが、安吾は親友の太宰治を自死で失ってからその事件をきっかけに、自分の作品で『死ぬことはいつでもできます、そんなつまらないことをしてはいけません』と述べているんです。
もちろん「山麓」は太宰の死よりもずっと前に発表された作品です。
でも、安吾の思想の根底には常にこの言葉があるような気がして…。
ちなみに安吾の代表作と言ったら「堕落論」がありますよね。
▼坂口安吾「堕落論」とは💡(AI による概要)
坂口安吾の『堕落論』は、太平洋戦争で敗北し、混乱する日本の社会で、旧来の道徳や倫理観を否定し、人間の「本然の姿」に戻ることの必要性を説いた評論です。敗戦で特攻隊員が闇市に堕ちるように、人間は堕落するものだと述べ、それは人間であるから、そして生きているから堕ちるのであり、人間性の回復こそが人を救う道だと論じました。
『堕落論』の要点
・時代の混乱と人間性の回復:戦後、日本は大きな混乱の中にありました。この混乱の中で、人々に道徳や倫理という「根拠のないおきて」を捨て、人間がもともと持つ弱さや脆弱さを受け入れること、すなわち人間であることの「堕落」を肯定することで、そこから人間性を回復し、明日へ踏み出すための指針を示すことを意図しました。
・「堕落」の肯定:敗戦により、それまで信じられていた倫理や道徳が崩壊しました。しかし、安吾はこれを単なる悪いことと捉えるのではなく、人間が本来持っている本質を露わにしたものと解釈しました。
・人間は弱く、だからこそ「堕ちる」:人間は本質的に脆弱で、常に堕落する可能性を秘めている存在だと安吾は考えました。人間の弱い部分を受け入れ、その弱さの中で、自分自身の救いを見つけることが大切だと説きました。
・「正しい堕ち方」の重要性:安吾は、完全な堕落には「鋼鉄のメンタル」が必要であり、人間はそこまで強くないため、結局は周りの規範やルールに従ってしまうと指摘します。だからこそ、人間は正しい道に堕ち切ることで、自分自身を発見し、救われなければならないと主張しました。
背景
・発表の時期と社会状況:坂口安吾の『堕落論』は、太平洋戦争が終結した直後の1946年(昭和21年)に雑誌『新潮』に掲載され、当時の日本社会に大きな反響を呼びました。
・現代における意味:敗戦直後の混乱した時代において、従来の価値観が揺らいだ人々に、自己の救済と人間性の再認識を促す、逆説的なメッセージとなりました。
私が解釈する坂口安吾作「堕落論」からのメッセージは“人間は堕ちるところまで堕ちたら、後は上がるのみ。だからとことん堕ちて、そこで自分自身を見つめ直し、そして再生して欲しい。”です。
「堕落論」は随筆で、「山麓」は小説という違いはあるものの、私は“両作品ともに伝えたい事は同じ”と考えています🧠
それをふまえて、ここから「山麓」の感想に参ります。
先ず「山麓」の冒頭文『あの頃私は疲れてゐた。遠い山麓の信夫の家で疲れた古い手を眺めてゐた、あの頃。』から、主人公は何かに疲れ、メンタルが酷く落ち込んでいる様子(=堕落)が窺えます。
きっと主人公はその疲れから解放されたくて、遠く離れた、白樺の林が繁るアイヌ族の信夫の家に療養に訪れたのでしょう。
私はアイヌ族、白樺という流れから“これは北海道の山麓に違いない‼️”と遠い北国の大自然に癒されたくなった主人公を連想しました。
次に『信夫には健康とアイヌ族の鼻髭があつた。信夫は毎日狩猟に行く。』という情景描写です。
私は“主人公が今最も欲している、自分が失ってしまった男らしさや力強さをあえて強調したのかな?”と思いました。
なぜならその描写から、原始的な生活で逞しく生きる信夫の人物像が否応なく想像させられたからです。
そして信夫は狩猟に行くとき、歩き方がひそひそと静かだという描写もあり、私は“猟師さんは獲物に自分の存在を悟られないよう山をひっそり歩くのだろう”と、信夫の日常をなお一層想像させられました💭
続いて、信夫を狩猟に送り出した後の信夫の奥さんの描写です‼️✨
面白いことに、主人公は信夫の留守中、奥さんの様子を細かく観察しているのですが、その観察によると、奥さんは遠くの空から銃声が聞こえると猟犬のように聞き耳を立て、信夫のことを想っているんだとか。
私はこのシーンにちょっぴり胸が熱くなりました💓
というのも信夫の鳴らす銃声は獲物を捕らえる時だけではないと理解できたからです。
冬間近、白樺の繁る山麓には熊だっているはず。
ましてや冬眠前の熊は、冬ごもりの準備のため、エサを大量摂取することに尽力しています。
となると、もしかしたら銃声は信夫と熊が遭遇し、命の対峙をしている時の音かもしれない🐻🔫⚡️‼️
だから奥さんは家にいる時も銃声が聞こえると信夫の身を案じ、方時もなくそわそわしている…。
そんな奥さんの姿が私の脳裏に浮かんできて、この描写がたまらなく愛おしくなりました。
別の日、信夫は珍しく獲物を仕留めて帰って来るのですが、信夫は獲物を後手に隠し、奥さんと主人公が獲物に気づくまで何も言わず、ただただ笑ってアピールしています😁
これは信夫の可愛らしい一面でしょうか💙⁉️
しばらくして、主人公は信夫の獲ってきた獲物に気付きます。
そして獲物の雉が縁側に置かれると、その置かれた時に鳴った音と美しい雉の姿に色々な想いが溢れ、信夫の家に来てから初めて笑うんです。
この描写は、主人公が信夫夫婦との時間や自然との共生の中で、やっと生きる意味を取り戻した瞬間を表現しているのかもしれません。
その後、主人公は感動的な場面にも関わらず信夫の奥さんの様子を細かく観察しています🔍‼️
奥さんは信夫の獲ってきた雉を膝に載せると何度も感想を呟き、信夫の顔を媚びるように見上げるんだとか。
このシーンの生々しさときたら…🙈💕
奥さんが信夫に惚れ直しているのが丸分かりです。
結果、主人公は信夫夫婦に魅せられ、病んだ心が解放されたのでしょう。
その夜『いつか健康を取戻した日、私も二連銃を肩にかけて、荒涼とした山麓をひそやかに通りたい』と思い続けるんです。
こうして物語は幕を閉じます。
つまり「山麓」は“主人公復活のフラグ”を示唆して完結したという事になります‼️
では振り返りのためもっと簡単に物語を要約してみましょう📝
主人公は堕落していました。
そこである山麓に辿り着きます。
その山麓にはアイヌ族の信夫の家があり、主人公は信夫夫婦とともに生活することでだんだんと心が洗われていきます。
ある日。
主人公は、信夫の獲って来た雉と奥さんの艶めかしさに魂を揺さぶられます。
それがトリガーとなり、最終的に主人公は“生きるとは何か”をゲットしました✊✨
いかがですか⁉️
「山麓」と「堕落論」、重なり合う部分があるでしょう。
人間は堕ちきったら、後は上がるのみ⤴️✨
底辺にいる時ほど自分を見つめ直す絶好のチャンス。
この機会に真の生き方を見つけ、再生&復活🌈✨
おそらくこれが安吾イズムであり、安吾スピリットで、「山麓」からのメッセージだと私は思いました。
皆さんは坂口安吾作「山麓」に、どのような感想を抱きましたか⁉️
▼坂口安吾に関連する記事


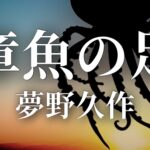


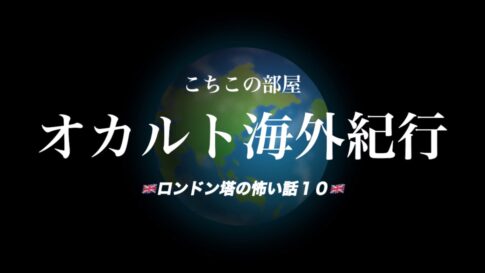



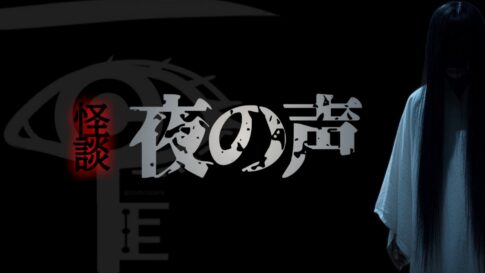
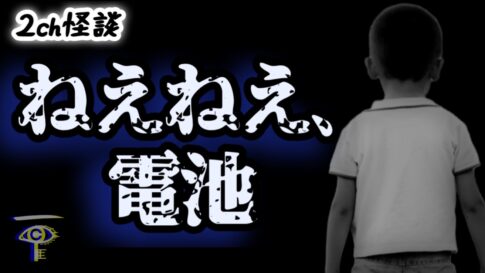


Xの画像、白樺が奥の奥まで続いていて、神秘的な雰囲気を醸し出していますね♫
主人公の名前がなかったり、内容も簡潔にまとめられていたりしていて、読者の想像力を掻き立てられる部分が、いろいろとありそうです。
1948年6月19日に太宰の遺体が見つかってから、およそ10日間で、安吾は3つの追悼エッセイを書いたということで、ものすごく無念さを持ったのでしょうね。
しんどいことも多いですが、安吾のメッセージを、ときどき読み返していきたいです。
utokyo318様✨
今回の白樺の画像は私のイメージ通りでめちゃくちゃ気に入ってます♪
安吾と太宰の関係…本当に盟友だった事が伝わってきます♡
そして安吾の堕落を肯定し尚「生きよ!」の姿勢からはある種の美学を感じます。やはり彼は生に執着した人という印象が強いです。
こんにちは♪
ブログも拝見しました
生成された画像、まさにその通りの画像にビックリ!!
雰囲気ありますよね
じーっと見ているとなんだかんだゾクゾクしましたよ
こちこさまが紹介された小説も時間あらときに読んでみますね
あ!
脱字にもなってまして、すいません(T_T)
絵文字も一緒に書いたのですが、反映されてなくてすいません(´Д`||)
がちょー様✨
白樺の林…素敵な仕上がりですよね♡
私も感動しちゃいました。
安吾の代表作「堕落論」からは、正に安吾スピリットが学べますよ♪
なっなんと!コメント欄は反映されない絵文字もあるのですね☆
こちらこそ、すみません(>人<;)